固定残業代とは、残業代をあらかじめ給与に含めて支給する制度です。制度そのものは合法ですが、求人票に正しく記載しなければ「違法」「労務トラブル」「応募減少」に直結します。本記事では、固定残業代の仕組み、メリット・デメリット、記載ルール、判例リスク、よくあるNG例やFAQまで解説します。
- 固定残業代とは?定義と仕組み
- 「固定残業代」と「みなし残業」の違い
- 求人票における固定残業代の記載ルール
- 固定残業代のメリット・デメリット
- 違法トラブルと判例リスク
- 固定残業代の相場と時間数設定
- FAQ(よくある質問)
- まとめ|固定残業代は「正しい理解と記載」がカギ
固定残業代とは?定義と仕組み
固定残業代は、企業の給与設計や求人票において必ず理解しておくべき基本制度です。まずは、制度の成り立ちや法律上の定義を確認し、その仕組みと計算方法を正しく押さえることが重要です。
定義
固定残業代とは、あらかじめ給与に一定時間分の残業代を組み込み、定額で支給する制度を指します。根拠は労働基準法第37条にあり、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働については割増賃金を支払う義務があります。一方で、所定労働時間を超えていても法定労働時間内に収まる労働については、法律上の割増義務はありません(ただし会社の規定により割増を支払うケースもあります)。企業はこうした残業代の支払い方法として「固定残業代」を導入でき、労働契約上の明示があれば有効です。
ただし、固定残業代の支給が「残業代の免除」を意味するわけではありません。実際の残業時間が固定時間を超えた場合は、必ず超過分を別途支給しなければならない という点を押さえる必要があります。
仕組み
固定残業代は「基本給」とは区別され、給与明細や求人票で明示されるべきです。
- 月給300,000円(基本給240,000円+固定残業代60,000円/30時間分を含む)
このように、①金額、②時間数、③超過分支給の有無を明示することが厚労省のガイドライン上の必須事項です。法律条文に直接規定されているわけではありませんが、記載が不十分だと「どこまでが基本給か不明確」とされ、裁判や労基署の調査で違法と判断されるリスクが高まります。
さらに、固定残業代は「毎月必ず一定額を支給する」仕組みであるため、実際の残業時間が少なくても控除することはできません。
固定残業代の計算方法
計算の基本は「基礎時給×割増率×固定時間数」です。
固定残業代の計算は、割増賃金や時間外手当の算定ルールに基づいて行う必要があります。計算方法を誤ると、最低賃金を下回ったり無効と判断される恐れがあるため注意が必要です。
- (1)基本給÷所定労働時間=基礎時給
- (2)基礎時給に割増率をかける
- (3)固定残業時間数をかけて固定残業代額を算出
【計算例】
- 基本給256,000円
- 所定労働時間160時間 → 基礎時給1,600円
- 残業割増率25% → 2,000円
- 固定残業30時間分 → 2,000円×30=60,000円
この場合、求人票には「固定残業代60,000円/30時間分」と記載するのが適切です。
「固定残業代」と「みなし残業」の違い
結論から言うと、「みなし残業」という制度は法律上存在しません。「みなし残業」という表現を求人票や労働条件通知書に記載すると、以下のリスクがあります。「みなし残業」という言葉を使うこと自体は違法ではありませんが、法律用語としては存在しないため誤解を招きやすいのが実態であるため、求人票では「固定残業代」と記載すること が望ましいです。
求人票における固定残業代の記載ルール
固定残業代を導入している企業が求人票を作成する際、もっとも注意が必要なのが「記載方法」です。
求人票は求職者が最初に目にする情報であり、曖昧な書き方や不十分な情報は、労務トラブルだけでなく応募数の減少にも直結します。
そのため、企業の採用担当者は、固定残業代を求人票に記載する際の基本ルールを正しく理解しておくことが不可欠です。
以下では、厚労省ガイドラインに基づいた「必ず記載すべき3要素」と、法的義務がある労働条件通知書との違いを解説します。
必ず記載すべき3要素(厚労省ガイドライン準拠)
求人票に固定残業代を記載する際は、厚生労働省のガイドラインで「必ず明示すべき」とされている3つの要素があります。
- 固定残業代の金額
- 対象となる時間数
- 超過分の支給有無
<これらはガイドライン上の推奨ではありますが、職業安定法や若者雇用促進法の運用とも関連しており、求人票に記載しないと「不十分」とみなされ、労基署から是正指導を受けたり、候補者から不信感を持たれる可能性があります。したがって、実務上は 必ず記載するべき必須要件 と考えて差し支えありません。
実務で使える文例(コピペ可)
求人票に記載する際は、以下のように正しく記載しましょう。
- 例1(営業職)
-
- 月給300,000円(基本給240,000円+固定残業代60,000円/30時間分を含む)。
- 30時間を超える時間外労働については、別途全額支給。
- 例2(エンジニア職)
-
- 年収4,200,000円〜5,000,000円(賞与含む)。
- 固定残業代:月45,000円/20時間分。20時間を超える残業代は別途支給。
- 例3(管理部門)
-
- 月給250,000円(基本給230,000円+固定残業代20,000円/10時間分)。
- 超過分は追加で全額支給。
ポイントは、求職者が見て「総額いくらなのか」「基本給はいくらか」「残業時間は何時間分か」がすぐに理解できることです。求人票を作成する際の注意点として、労働基準法や36協定との整合性を確認し、最低賃金を下回らないかを必ずチェックしてください。
NG例と改善例の比較表
求人票でよく見られる「不適切な書き方」と「改善例」を比較すると次のようになります。
| NG例 | 改善例 | リスク/効果 |
|---|---|---|
| 月給300,000円(みなし残業代含む) | 月給300,000円(基本給240,000円+固定残業代60,000円/30時間分)超過分は全額支給 | 「みなし残業」という表現は法的根拠がなく、誤解につながる |
| 固定残業代あり(詳細は面談時) | 固定残業代:60,000円/30時間分。超過分は別途全額支給 | 記載不足により労基署から是正勧告を受けやすい |
| 固定残業代50,000円(超過分支給なし) | 固定残業代50,000円/25時間分。超過分は別途全額支給 | 「超過分不支給」は確実に違法 |
| 月給300,000円(固定残業代を含む) | 月給300,000円(基本給240,000円+固定残業代60,000円/30時間分) | 基本給と手当の区分不明 → 無効と判断されやすい |
このように、求人票の表記ひとつで「違法リスク」や「応募率」が大きく変わります。
記載方法のポイントまとめ
- 必須要素を3点すべて記載(金額・時間数・超過分支給)
- 基本給と固定残業代を区別して明記
- 「みなし残業」という言葉は使わない
- 求人票と労働条件通知書の内容を一致させる
これらを徹底することで、労務リスクを避けながら、求職者にとって分かりやすく信頼性のある求人票を作成できます。
固定残業代のメリット・デメリット
企業にとってのメリット
固定残業代を導入することで、企業側には以下のメリットがあります。
- 人件費の見通しが立てやすい
残業代が毎月一定額で計上されるため、予算管理がしやすくなります。 - 給与額をわかりやすく提示できる
求人票に「月給30万円」と表示できるため、求職者にとって給与水準のイメージがしやすい。 - 求職者へのアピール
残業が少なかった月でも固定残業代は全額支給されるため、結果的に実残業時間が少なければ「高収入」に映るケースがあります。
企業側にとってのメリットは人件費の見通しが立つことですが、平均的な残業時間と比べて過大な設定をしてしまうと、応募者からは「長時間労働が前提では」と受け取られるデメリットにつながります。
企業にとってのデメリット
一方で、導入・運用を誤ると企業にとって大きなリスクになります。
- 法的リスク
時間数や金額を明記しなかった場合、労基署の是正勧告や裁判で「未払い残業」と認定されることがあります。 - 求職者からの敬遠
固定残業代を「ブラック企業の象徴」と捉える求職者もおり、応募率が下がる可能性があります。 - 基本給が低く見えやすい
固定残業代を多めに設定すると「基本給が低い=昇給や賞与に不利」という印象を持たれることがあります。
求職者にとってのメリット
求職者側にとっても、固定残業代には一定の利点があります。
- 給与の下限が保証される安心感
実際の残業が少なくても固定残業代は支給されるため、「必ず一定の収入が確保される」メリットがあります。 - 給与総額のイメージがつきやすい
求人票で「月給30万円」と提示されると、求職者は生活設計を立てやすくなります。
求職者にとってのデメリット
しかし、誤解や不満を生みやすい制度でもあります。
- 「残業が前提」と誤解される
固定残業代の表記だけを見ると「必ず残業しないといけないのでは?」と誤解する求職者もいます。 - 超過残業の不満
実残業時間が固定時間を大きく上回ると、「固定残業代では足りない」と不満につながる。
違法トラブルと判例リスク
よくある違法ケース
固定残業代制度は適切に運用すれば合法ですが、記載や運用を誤ると「違法」と判断されることがあります。代表的なケースは以下のとおりです。
- 基本給と手当の区分が不明確
「月給30万円(固定残業代含む)」としか記載していないケース。どこまでが基本給でどこからが固定残業代か不明なため、裁判で「全額を基本給」とみなされるリスクがあります。 - 超過分を支給しない
「固定残業代に含まれる」として、実際の残業が固定時間を超えても追加支給を行わないケース。これは確実に違法です。
裁判例・労基署事例
実際に固定残業代をめぐる裁判や労基署の指摘は多数あります。
- 最高裁判例(大成建設事件、2014年)
「基本給と固定残業代の区分が明確でない場合、固定残業代の有効性は否定される」と判断。結果、固定残業代部分は基本給と認定され、追加の残業代支払いが命じられました。 - 中小企業の労基署是正事例
「固定残業代○万円」とだけ求人票に記載し、労働条件通知書にも時間数が明示されていなかった。労基署調査で「未払い残業」と認定され、数百万円の遡及支払いを命じられた。 - IT企業での事例
求人票に「みなし残業代30時間分含む」と記載していたが、労働契約書には具体的な時間数がなく、トラブルに発展。裁判で「30時間分の有効性は否定」され、超過分含め追加支給を命じられた。
固定残業代の相場と時間数設定
業界ごとの相場
固定残業代に設定される時間数は、職種や業界によっておおよその相場があります。下記は一例です。
- 営業職:20〜40時間/月
外回りや商談対応で残業が発生しやすいため、比較的高めに設定される傾向があります。 - ITエンジニア・Web系職種:30〜45時間/月
プロジェクト進行やリリース前の残業が多い業界。求人票上は30時間分を設定するケースが一般的。 - 管理部門(人事・経理など):10〜20時間/月
比較的残業が少ないため、低めに設定されることが多い。
このように職種ごとに傾向はありますが、「時間数が高ければ優秀な人材が集まる」というわけではなく、むしろ応募者から敬遠される場合もあります。
固定残業時間数の設定を誤るとどう見られるか
固定残業代の時間数は「高すぎても低すぎても」問題になります。相場より極端に高い時間数を設定すれば、候補者から「長時間労働が前提なのでは」と不安視され、応募が減少する恐れがあります。一方で実際の平均残業時間よりも低い時間数で設定してしまうと、超過分の残業代支払いが毎月発生し、「求人票の給与イメージと違う」と候補者から不信感を持たれるリスクがあります。時間数設定は実態に即し、業界相場を参考にしながら適切に設計することが重要です。
適切な時間数を決めるポイント
固定残業代の時間数は、以下の観点から設定すると適切です。
- 実際の平均残業時間をもとにする
過去1〜2年の勤怠データを確認し、平均残業時間に近い数値を採用。 - 業界・職種の相場を参考にする
営業は30時間前後、エンジニアは40時間前後、管理部門は20時間以下が一般的。 - 求職者心理を考慮する
高時間数は応募減少につながるため、相場を超える設定は避ける。 - 柔軟な制度設計
「30時間分」など標準的な設定にしつつ、繁忙期には実残業を追加で支給する運用が望ましい。
FAQ(よくある質問)
問題になるのは、求人票に金額や時間数を明記していない場合や、超過分を支給しないなど誤った運用をしている場合です。
正しく記載・運用していれば法律上はまったく問題なく、むしろ「人件費の見通しが立てやすい」「候補者に給与総額をわかりやすく示せる」といったメリットもあります。
つまり、制度が危険なのではなく、誤った使い方をする企業がブラックに見えるのです。
ただし、労働基準法や36協定では「時間外労働は原則として月45時間以内」と定められており、この範囲を大きく超える設定は「長時間労働が前提ではないか」と疑われ、候補者から敬遠されやすくなります。
実際の求人票では、営業職で30時間前後、エンジニア職で40時間前後、管理部門では20時間以下といった時間数を設定するケースが多く見られます。統計的に裏付けられた「相場」というわけではありませんが、求人市場で一般的に流通している水準として参考になります。
たとえば30時間分の固定残業代を支給していて、その月の残業が10時間しかなかったとしても、30時間分は満額支給が必要です。
これは「従業員にとってのメリット」でもあり、企業にとっては制度設計上の留意点となります。
これらを固定残業代に含める場合は、内訳や計算根拠を就業規則や労働条件通知書に明記することが不可欠です。
曖昧なままでは無効とされ、未払い残業代の請求リスクにつながります。
実務上は「割増賃金の前払い」という性質から、基本給に含めず、賞与や退職金の算定対象外とするケースが多く見られます。
ただし、これはあくまで各企業の就業規則や賃金規程によって異なり、「算定基礎に含める」と定めている会社も存在します。
したがって、求人票や雇用契約書の段階で「賞与や退職金の算定に固定残業代を含めるかどうか」を明示しておくことが、候補者の誤解や入社後のトラブルを防ぐうえで望ましい対応といえます。
役職名だけで自動的に管理監督者と認められるわけではなく、実際に労働時間の裁量を持っているかどうかで判断されます。
そのため、労基法上の管理監督者に該当する場合は固定残業代を支給する必要はありませんが、一般的な「課長職」や「係長職」など、実態として残業代の支給対象とされる管理職には、固定残業代を設けている企業も存在します。
重要なのは「管理職だから一律に支給しない/支給する」ではなく、その役職が労基法上の管理監督者に該当するかどうかを正しく判断し、就業規則や労働契約書に明記することです。
まとめ|固定残業代は「正しい理解と記載」がカギ
固定残業代は、法律に基づいた有効な制度であり、適切に活用すれば企業にとっても求職者にとってもメリットがあります。
しかし、求人票での誤った記載や超過分の未払いは、違法リスク・労基署からの是正・採用ブランドの低下につながるため注意が必要です。
企業が求人票を作成する際に必ず押さえるべき3つの原則は以下のとおりです。
- 金額・時間数・超過分支給の有無を明記する
- 基本給と固定残業代を明確に区分する
- 求人票・労働条件通知書・就業規則の内容を一致させる
この3点を徹底すれば、法的リスクを避けながら、候補者にとって信頼性の高い求人票を提示できます。
固定残業代は「ブラック」な仕組みではなく、正しい運用をすれば採用力を高める武器になります。
人材紹介会社と企業の採用担当者にとって、固定残業代を正しく理解し、求人票に適切に反映することは紹介や採用成功の前提条件です。制度を誤解したまま求人を出すと、候補者からの不信感や労務トラブルにつながりかねません。
クラウドエージェントでは、こうした課題に直面する人材紹介会社や採用担当者をサポートし、求人票のチェックや改善提案を通じて安心して活動を進められるよう支援しています。ぜひご活用ください。
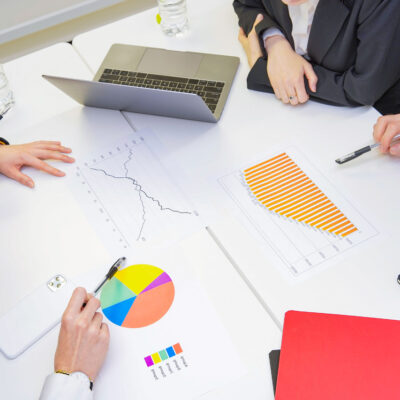
















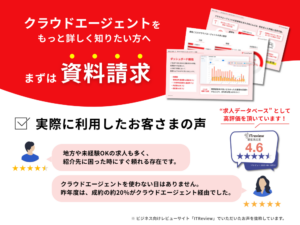















この記事へのコメントはありません。