「業務委託で人材紹介を行う」というフレーズを耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。副業解禁や働き方の多様化を背景に、フリーランスや業務委託で働く人が増えるなか、「人材紹介も委託できるのでは?」と考える方が出てきています。例えば、新規事業として有料職業紹介の許可を取得した会社が、事業拡大のために経験豊富なエージェントと業務委託契約を結び、人材紹介業務を任せる。一見すると合理的で、双方にとってメリットがあるように思えます。では、実際にこのような形態は合法なのでしょうか?
本記事では、人材紹介を業務委託で行う際の仕組みや違法性の有無、合法となるケース、注意すべき点についてわかりやすく解説します。
業務委託での働き方とは?
雇用契約との違い
業務委託とは、企業と雇用契約を結ばず、一事業主として業務を請け負う働き方を指します。雇用契約の場合は、労働時間や勤務場所が会社により管理され、社会保険への加入や雇用保険の適用も受けられます。一方で業務委託は、成果物や遂行した業務に応じて報酬を受け取るスタイルであり、雇用契約とは根本的に異なります。
このため「自由度が高い反面、保障が少ない」という特徴があります。労働基準法の労働者保護も適用されず、報酬の支払い遅延や契約打ち切りのリスクもあるため、契約書の内容をしっかり確認することが欠かせません。
他業種での事例
- ITエンジニア・Webデザイナー:契約形態はさまざまで、成果物を納品して報酬を得る「請負契約」のほか、時間単価制で稼働時間に応じて報酬が支払われる「準委任契約(SES契約など)」も多い。プロジェクト単位・スポット契約のいずれも存在し、スキルや案件内容によって働き方を選べる。
- 営業代行:新規顧客開拓や商談セッティングを成果報酬型で請け負うケースが多いが、固定報酬+成果報酬のハイブリッド契約も見られる。
- ライターやコンサルタント:記事の納品やアドバイザリー契約など、納品型の契約が主流だが、月額顧問料形式や時間単位契約で報酬を受け取る場合もある。
このように、業務委託は必ずしも「納品型」に限定されず、案件内容や契約形態によって柔軟に設計されているのが特徴です。しかし、人材紹介については事情が異なり、免許制という厳しい規制が存在します。
人材紹介の業務委託契約とは?
免許取得が必須である理由
人材紹介は厚生労働省の管轄下にある「許認可事業」です。有料職業紹介を行うには、厚生労働大臣からの免許を事業所ごとに取得する必要があります。免許を持たない状態で人材を紹介し、報酬を受け取れば職業安定法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
さらに、免許を取得するには資産要件や事務所要件が課されます。例えば、純資産が500万円以上あること、プライバシーが確保された事務所を構えていること、職業紹介責任者を配置していることなどです。個人がこれらを満たすのは難しく、多くの場合は法人としての参入が前提となります。
人材紹介の業務委託契約の仕組み
人材紹介における業務委託契約というと、しばしば「免許を持つ紹介会社が外部の人材と契約を結び、その会社の看板のもとで紹介業務を行わせる」といったイメージを持たれることがあります。さらに「成果報酬制で、紹介が成功した場合のみ報酬が発生する」という仕組みを想像する方も少なくありません。
しかし、このような形態はあくまでイメージ上の話であり、実際には職業安定法に違反する可能性が非常に高い点で注意が必要です。
業務委託で人材紹介を行うとどうなる?
受託者(エージェント側)のメリット
- キャリアコンサルティングやマッチング業務に専念できる
- 成果報酬制のため、実力次第で高収入を得られる
- 雇用関係ではないため、働き方の自由度が高い
- 個人事業主としても許可を取得すれば人材紹介事業に携われる
他の人材紹介会社にてエージェントを経験している方や、人事・採用経験が豊富にあり、中途採用の流れを理解している方などが、新たな選択肢として業務委託での人材紹介を検討するかと思います。これまで会社員として、収入は固定給で安定していたものの、より自分の実力に直結した働き方が魅力に感じるのかもしれません。
企業側(委託する側)のメリット
- 教育コストや人件費がかからない
- 成果が出たときだけ報酬を支払うためリスクが低い
- 優秀な人材を外部パートナーとして活用できる
- 事業拡大をスピーディに進めやすい
社員を抱えていた際は、従業員が成約してもしなくても給与を支払わなければなりませんが、業務委託で成果報酬制を導入すれば、内定承諾した場合のみ対価を支払えばいいのでリスクが非常に低くなります。
しかし…人材紹介を業務委託で行うのはほぼ不可能?
人材紹介を業務委託で行うことは、実際には法律上ほぼ不可能です。その最大の理由は「名義貸し」にあたるからです。
人材紹介は国の許可を受け免許を持った事業者しか行えません。免許のある事業者が、業務委託で外部の人に紹介を任せてしまうと、その人は自らの事業としてではなく、他社の名義を借りて紹介業務を行うことになります。これを「名義貸し」と呼び、名義貸しは職業安定法で禁止されています。たとえその業務委託を受けた外部の人が人材紹介の免許を持っていたとしても、他社の看板のもとで紹介を行うことは「名義貸し」となってしまうため、できません。
したがって、業務委託という形で人材紹介を行うのはほぼ不可能なのです。
違法と判断された場合のリスク
もし違法と見なされた場合、以下のリスクが生じます。
- 刑事罰:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 行政処分:事業停止命令、免許取り消し
- 信用失墜:企業・個人ともに業界内での信頼を失い、再参入が困難になる
また、受託者本人だけでなく、委託した紹介会社側も処分対象となる点に注意が必要です。
では人材紹介を業務委託するにはどうすればよいのか?
個人で人材紹介に携わりたい場合
自ら有料職業紹介の免許を取得するか、免許を持つ人材紹介会社に所属することが必要です。
事業所が人材紹介事業を効率化したい場合
違法な業務委託ではなく、求人データベースや採用管理ツールを活用し、正規の手法でマッチング力を高めましょう。
まとめ
人材紹介事業の業務委託契約が法に触れるのかどうか、その視点について解説をしました。
業務委託という働き方は多様化する社会において確かに広がりを見せていますが、人材紹介については「免許制」という強い規制があるため、業務委託で行うことは違法リスクが極めて高いのが現実です。フリーランス的な柔軟性を求める場合でも、必ず法令を遵守し、正しい方法で人材紹介事業に関わる必要があります。
Crowd Agent Mediaを運営しているCrowd Agent(クラウドエージェント)では、人材紹介の売上をあげるための集客テクニックや、効率的な求人開拓の手法、最新の人材業界ニュースや事業運営ノウハウなど、様々な課題を解決するセミナーを開催しております。どのセミナーも無料で参加できるので、どうぞお気軽にお申し込みください。
また、Crowd Agent(クラウドエージェント)は、求人数No.1の人材紹介会社向け求人データベースです。今すぐ10,000件以上の求人を、自社求人と同じように活用することが可能です。未経験求人からミドルクラス〜ハイクラス層、また地域採用なども幅広く取り扱いしております。豊富な求人を手に入れ、高単価成約を目指していってはいかがでしょうか?ぜひ一度資料請求をしてみてください。
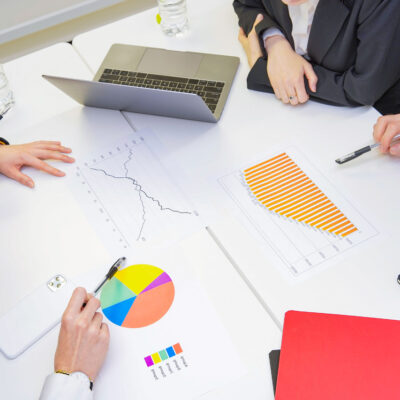


















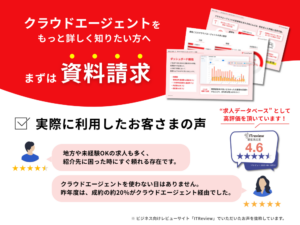













この記事へのコメントはありません。