職業紹介は、求人企業と求職者を結びつける仕組みとして、採用や転職活動で広く利用されています。公共のハローワークや民間の紹介会社など、さまざまな職業紹介の窓口があり、効率的にマッチングを進められるのが大きな特徴です。本記事ではその制度や役割を解説します。
職業紹介とは
職業紹介とは、求人企業と求職者の間に立ち、雇用契約の成立を仲介する制度です。職業安定法第4条第1項では、「求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間で雇用関係の成立をあっせんすること」と定義されており、法的に根拠づけられています。
この制度の最大の特徴は、労働者を自社で雇用しないことにあります。たとえば人材派遣では派遣会社が労働者を雇用し、派遣先で働かせる仕組みですが、職業紹介では紹介会社はあくまで仲介者であり、最終的な雇用契約は求人企業と求職者の間で直接結ばれます。給与や福利厚生の提供主体も求人企業です。
職業紹介の歴史は戦後にさかのぼります。第二次世界大戦後の失業問題を背景に、1947年に職業安定法が施行され、国による公共職業紹介所が設置されました。その後、1980年代の規制緩和によって民間の有料職業紹介事業が拡大し、今日の人材紹介業へと発展しています。
現在の労働市場では、専門スキルを持つ人材の獲得競争が激化しています。特にIT、医療、介護などの分野では、職業紹介を通じた採用が重要な役割を果たしています。企業は効率的に適材を採用でき、求職者は希望条件に合った企業と出会える可能性が高まるのです。
職業紹介所とは
「職業紹介所」とは、職業紹介を利用できる窓口や施設を指します。法的な用語ではなく、利用者目線での表現ですが、就職・転職活動の現場では広く使われています。
公共の場合
代表例はハローワークです。全国に500か所以上設置されており、誰でも無料で利用できます。提供されるサービスは多岐にわたり、求人紹介だけでなく、履歴書や職務経歴書の添削、模擬面接、職業訓練の案内、雇用保険の手続きなども行われています。特に失業中の人にとっては、失業給付と就職支援を一体的に受けられる点が大きなメリットです。
民間の場合
一方で、リクルートエージェント、doda、JAC Recruitment などの民間人材紹介会社も「職業紹介所」と呼ばれることがあります。これらは有料職業紹介事業として運営されており、求人企業からの成功報酬を収益としています。利用者は無料で登録でき、キャリアカウンセリング、求人の紹介、非公開求人へのアクセス、年収交渉の代行など、手厚いサービスを受けられるのが特徴です。
公共と民間ではサービス内容や対象が異なりますが、どちらも「求職者と求人企業をつなぐ窓口」という点では共通しています。
無料と有料の紹介事業の違い
職業紹介は、求職者または求人者から手数料などの対価を受け取るかどうかによって「有料」と「無料」に区分されます。
前述した、公共の職業紹介所は無料職業紹介事業に、民間の職業紹介所は有料職業紹介事業にあたります。
無料職業紹介事業(=公共が中心)
無料職業紹介事業は、公的機関や学校、商工会議所、農協などが運営し、利用者から料金を徴収しません。前述した公共の職業紹介所(ハローワークや大学キャリアセンターなど)がこれにあたります。大学の就活支援や自治体の雇用促進など、地域・社会的な目的で展開されるのが特徴です。
有料職業紹介事業(=民間が中心)
有料職業紹介事業は、求人企業から成功報酬を受け取る営利型ビジネスです。前述した民間の職業紹介所(リクルートエージェント、doda、JAC など)がこれに該当します。報酬額は採用者の年収の30〜35%が一般的で、年収500万円の人材を紹介した場合は100万〜175万円程度の手数料が発生します。外資系や専門職に特化した紹介会社も多く、求職者は希望条件に沿った求人を効率よく探せるのが魅力です。
なお、非営利団体であっても紹介によって収益を得れば「有料職業紹介」として扱われるため注意が必要です。
職業紹介所を設立する流れ
日本にある職業紹介所の大半は民間が運営する有料職業紹介事業です。厚生労働省の「令和5年度 職業紹介事業報告書(速報)」によれば、有料職業紹介事業所は29,171事業所、無料職業紹介事業所は1,120事業所とされています。数としては圧倒的に民間が多く、これから新しく設立を目指す場合も基本的には有料職業紹介事業になります。なお、公共の職業紹介所は国や自治体が担うものであり、民間が新規で設立することはできません。そのため、ここでは有料職業紹介事業を設立する流れを説明します。
新しく有料職業紹介事業を立ち上げるには、厚生労働大臣の許可(免許)を取得する必要があります。許可取得までの一般的な流れは以下のとおりです。
- 資本金・財務要件を整える
純資産500万円以上、現預金150万円以上を用意します。決算書や納税証明書で確認されるため、資金準備は最初の大きなステップです。 - 事務所を準備する
事務所は事業に使用し得る面積が概ね20㎡以上、個人情報を管理できる構造であることが条件です。自宅を利用する場合は生活スペースと明確に分ける必要があります。 - 職業紹介責任者を選任する
1名以上の責任者を常勤で配置し、講習を受講して修了証を取得する必要があります。設立の早い段階で人選を進めておくことが重要です。 - 許可申請を行う
厚生労働大臣への申請に必要な書類(申請書、登記事項証明書、財務書類、事務所の賃貸契約書など)を揃えて提出します。 - 審査・許可を受ける
書類審査を経て、問題がなければ許可が下ります。初回の有効期間は3年で、以降は5年ごとの更新が必要です。
企業が職業紹介を活用するメリット
ここでは求人企業にとって、職業紹介所を利用するメリットがどこにあるのかを説明します。
採用コストの削減
マイナビの「中途採用状況調査2025」によると、中途採用にかかる1人あたりの転職サイト求人広告費は平均37.0万円でした。また、求人広告費全体の年間実績平均は134.6万円、1社あたりの年間採用費総額は650.6万円にのぼります。こうしたコストは決して小さくありません。
職業紹介所は成功報酬型のため、選考を進めても雇用契約に至らなければ費用は発生しません。さらに、自社で募集から書類選考までを行うと人材や時間が取られてしまいますが、職業紹介所に委託することで社員の負担を大幅に軽減できます。
参考:中途採用状況調査2025年版(2024年実績)(マイナビ)
非公開求人の活用
職業紹介所の大きなメリットは、非公開求人に対応していることです。中途採用の場合、大手が求人を公開募集すると応募が殺到し、対応にかなりの負担を強いられます。非公開求人で職業紹介所に依頼すれば、条件に合う人材を選考してもらえので業務負担が軽減できます。
また、新規プロジェクト要員や重要ポストの欠員など他社に動向を知られたくない募集などの際にも、非公開求人が役立ちます。急な欠員に対して早急な穴埋めが必要な場合も、予め条件に合った人材を紹介してもらえるので、選考時間を短縮できます。
非公開求人を利用することは、必要十分なスキルを持った人材を第三者の視点から見極め、紹介してもらえるので、採用負担の軽減が望めます。
採用業務の効率化
採用活動では、求人原稿の作成や掲載、応募者管理、書類選考、面接日程の調整など、細かな業務が数多く発生します。人事担当者がこれらをすべて対応すると、多大な時間と労力がかかり、本来注力すべき「候補者の見極め」や「入社後の定着支援」に割けるリソースが不足してしまいます。
職業紹介所を利用すれば、求人要件に合う候補者のリストアップや書類選考の一次スクリーニングを代行してもらえるため、効率的に母集団形成が可能です。また、エージェントが応募者とのやり取りや面接調整までサポートすることで、企業側は最終候補者との面接に集中できます。
この結果、採用スピードの向上と採用精度の改善が期待でき、採用活動全体の生産性を高めることにつながります。
求職者が職業紹介を活用するメリット
転職を行う求職者にとって職業紹介所を活用するメリットはどのようなものがあるでしょうか。ここでは求職者が職業紹介所を利用するメリットについてみていきましょう。
仕事をしながら仕事を探せる
求人広告などを利用する場合、自身で条件に合う転職先を見つけて、応募から応対、面接など全て自分で行う必要があります。広告から自分の希望に沿った求人を探すだけでも労力を要します。
職業紹介所に登録すれば、そのノウハウから自分に合った仕事を見つけてもらえるので、全てを自分でする必要がなく仕事を続けながらでも仕事が探せる場合が多いです。効率的に転職先を探すことができ、それでいて登録費用などは原則発生しないので、経済的にも負担を軽減することが可能です。
面接や履歴書などのサポートを受けられる
職業紹介所では求人に対するマッチングのためにさまざまなサポートを行っているところもたくさんあります。仕事の紹介だけでなく、面接応対の仕方や履歴書、職務経歴書のチェックを無料でしてもらえます。
求人企業の雰囲気や職場環境など、労働条件や環境についても事前に確認することができ、ひとりでは難しい給与などの条件交渉についても担当者に相談や依頼ができるため安心感にも繋がります。
条件交渉の代行
転職活動において多くの人が悩むのが、給与や労働条件の交渉です。自分から切り出すのは心理的なハードルが高く、提示条件をそのまま受け入れてしまうケースも少なくありません。職業紹介所を通じて応募した場合、エージェントが企業との間に立って条件交渉を行ってくれるため、求職者は安心して希望を伝えることができます。
たとえば「年収をもう少し上げたい」「残業時間を抑えたい」といった要望も、第三者であるエージェントから企業に伝えてもらうことで、スムーズかつ角が立たない交渉が可能になります。結果的に、入社後のミスマッチや早期退職のリスクを減らす効果も期待できます。
非公開求人へのアクセス
職業紹介所を利用する大きなメリットのひとつが、非公開求人に出会えることです。非公開求人とは、企業が採用活動をオープンにせず、限られた紹介会社だけに依頼している求人のことです。経営幹部や専門職、急募案件などが多く含まれ、一般的な求人サイトや広告では見られない情報にアクセスできます。
特に大手企業や外資系企業では、採用活動を外部に知られたくない理由から非公開で人材を探すケースも多く見られます。職業紹介所を通じて登録することで、こうした「掘り出し物の求人」に応募できる可能性が広がり、自力での転職活動では得られない選択肢を確保できます。
まとめ
職業紹介は、求人企業と求職者をつなぐ重要な仕組みであり、公共の職業紹介所(無料職業紹介事業)と民間の職業紹介所(有料職業紹介事業)の両方で活用されています。公共は社会的・公共的な雇用促進を担い、民間は専門性やスピードを活かして効率的なマッチングを提供しています。
企業にとっては、採用コストの削減や非公開求人の活用、採用業務の効率化といったメリットがあり、求職者にとっては、仕事を続けながら転職できる環境や、応募書類・面接のサポート、条件交渉の代行、非公開求人へのアクセスといった利点があります。
今後も労働市場の変化に伴い、職業紹介の役割はさらに拡大していくことが予想されます。制度や仕組みを正しく理解し、自社や自身の目的に合わせて公共・民間を使い分けることで、採用活動・転職活動をより有利に進めることができるでしょう。
クラウドエージェントは10,000件以上の求人を今すぐ使える人材紹介会社向け求人データベースです。未経験の候補者向け求人から、経験豊富な候補者に向けた求人まで、幅広く扱っていただくことが可能です。転載可能求人もあるため、候補者集客にもご利用いただけます。紹介事業でお困りの際はお気軽にこちらからご相談ください。
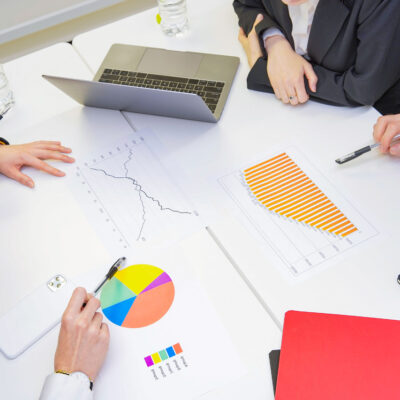































この記事へのコメントはありません。