有料職業紹介事業とは、人材紹介業の一形態で、求人企業と求職者を結びつける際に紹介手数料を受け取るモデルを指します。事業を始めるには厚生労働大臣の許可(免許)を受ける必要があり、資本金や事務所の条件、責任者の配置など、いくつかの要件を満たさなければなりません。本記事では、有料職業紹介事業の基本から免許取得の流れ、必要な準備や費用、更新の注意点までを、初めての方にもわかりやすく解説します。
- 有料職業紹介事業とは?
- 有料職業紹介事業を始めるには?
- 有料職業紹介事業の免許取得に必要なお金の準備
- 有料職業紹介事業の免許取得に必要な場所の準備
- 有料職業紹介事業の免許取得に必要な資格の準備
- 有料職業紹介事業の免許取得に必要な書類の準備
- 有料職業紹介事業の免許申請の流れ
- 有料職業紹介事業の免許取得後の更新と注意点
- 有料職業紹介事業に関するよくある質問(FAQ)
- まとめ:有料職業紹介事業について理解しよう
有料職業紹介事業とは?
人材紹介との違い
有料職業紹介事業は、企業と求職者の間に立ち、マッチングが成立した際に紹介手数料を受け取る仕組みです。人材紹介には「有料」と「無料」の2種類があり、ハローワークや大学キャリアセンターが行うものは無料職業紹介、民間企業が行うものは有料職業紹介事業に分類されます。一般的に「人材紹介」と呼ばれるものは、有料職業紹介事業を指しているケースが多いです。
人材派遣との違い
人材派遣は、派遣会社が労働者と雇用契約を結び、派遣先企業に労働者を派遣する仕組みです。この場合、給与の支払いは派遣会社が行います。
一方、有料職業紹介事業は、求職者と紹介先企業が直接雇用契約を結ぶ点が大きな違いです。紹介会社は給与を支払わず、採用が決定した時点で紹介手数料を受け取ります。
有料と無料の職業紹介の違い
前述のとおり、職業紹介事業には「有料」と「無料」があります。有料職業紹介事業は採用決定時に手数料を受け取る仕組みで、民間の人材紹介会社の多くが該当します。一方、ハローワークや自治体・大学の就職課などは無料職業紹介にあたります。
なお、有料・無料を問わず、職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可(免許)が必要であり、許可証(免許証)が交付されて初めて事業を開始できます。
収益の仕組み
有料職業紹介事業の収益は、紹介先企業から受け取る手数料です。相場は採用された人材の理論年収の30〜35%程度です。例えば、年収500万円の人材を紹介した場合、150〜175万円の手数料を受け取る形です。業界や職種によって水準は異なり、専門職や管理職では40%を超えることもあります。
有料職業紹介事業を始めるには?
有料職業紹介事業を始めるためには、厚生労働大臣の許可(免許)を取得することが必須です。許可を受けると「職業紹介事業許可証(免許証)」が交付され、求人企業との契約や求職者の登録を正式に行えるようになります。
開業にあたって準備すべきことは大きく分けて4つです。
お金の準備
前提条件としての財産要件を満たす必要があるだけでなく、初期費用、運営費用が必要になります。
場所の準備
事業を行うオフィスには、専用性・独立性・プライバシー確保が求められます。自宅やシェアオフィスであっても、専用の区画があり、面談内容が外部に漏れない環境であれば認められるケースがあります。一方で、短期貸しやフリーアドレス型で区画が不明確なオフィスは不可とされることがあります。なお、従来言われていた「20㎡以上」といった面積の数値要件は現在は存在せず、労働局は「業務に適切な広さかどうか」を重視しています。
資格の準備
各事業所には1名以上の「職業紹介責任者」を配置しなければなりません。資格といっても特別な国家資格ではなく、厚生労働省指定の講習(1日、1万円前後)を受講して修了証を取得すれば要件を満たせます。
書類の準備
許可申請には、申請書、登記事項証明書、財産証明、事務所の平面図・写真、職業紹介責任者の修了証など多数の書類が必要です。いずれも形式だけでなく、実際に要件を満たしているかどうかの根拠資料として審査されます。
次章からは、それぞれの準備内容について詳しく解説していきます。
有料職業紹介事業の免許取得に必要なお金の準備
有料職業紹介事業を始めるにあたり、まずは財産要件を満たすことが大前提となります。そのうえで、免許申請までに必要な初期費用と、事業を運営していくための費用を準備しなければなりません。ここでは「前提条件 → 初期費用 → 運営費用」の順に整理します。
財産要件(前提条件)
免許申請では、財産要件を満たしていなければ申請自体が受理されません。
- 純資産が500万円以上あること
- 現金・預金が150万円以上あること
これらは単なる口頭確認ではなく、決算書や残高証明といった財務書類を提出して確認されます。資本金が多くても借入が多ければ純資産はマイナスとなり、申請は不許可になります。
初期費用(免許取得までに必要な費用)
財産要件をクリアしたうえで、免許申請までに次の費用が必要です。
- 登録免許税:9万円
有料職業紹介事業の許可申請には、登録免許税法別表第一第81号に基づき、1件につき9万円の登録免許税が必要です。納付は銀行や税務署(歳入代理店)での現金納付が原則で、領収証を申請書に添付します。不許可となった場合でも返金はされません。
- 職業紹介責任者講習の受講料:おおむね1万円前後(8,800〜13,400円程度)
各事業所に1名以上配置が必要。講習は1日で修了でき、修了証が免許申請に必須です。
- オフィス関連費用:数十万円〜
賃貸オフィスの保証金・敷金、内装工事(面談室の設置やパーテーション)、机や椅子などの備品購入費用がかかります。
これらを合計すると、最低でも数十万円〜100万円程度の初期投資が必要となります。
運営費用(免許取得後にかかる費用)
免許を取得しても、収益が安定するまでは数か月の時間がかかるため、運転資金の確保も欠かせません。
- 求人広告・媒体費用:数十万円〜
求人サイトやスカウト媒体への掲載に必要です。
- 人件費:月数十万円〜
営業担当やキャリアアドバイザー(CA)を雇う場合の給与。
- システム利用料:月1〜3万円程度
求人管理システム(ATS)や候補者データベースの利用料。
開業から黒字化するまでの期間は業種や規模によって大きく異なります。一般的な起業全体では、1年目で黒字化する割合は2割弱にとどまり、3〜5年を見込むのが一般的です。一方で、人材紹介事業は在庫や大規模設備投資が不要で、成功報酬型の収益モデルであるため、早ければ1年前後で黒字化するケースもあります。ただし確実ではないため、複数年分の運転資金を確保しておくことが安定した事業運営につながります。
有料職業紹介事業の免許取得に必要な場所の準備
有料職業紹介事業を行うには、専用性・独立性・プライバシーが担保される事務所を確保することが必須です。財産要件と並んで審査で重視されるポイントであり、申請後は書類審査や現地調査で基準を満たしているか確認されます。もし不備があれば補正や改善を求められ、最終的に要件を満たさなければ不許可となります。
面積と専用スペース
事務所の面積については下記の点に注意しましょう。
- 事務所は当分の間、概ね20㎡以上あれば要件を満たすものとされています。20㎡未満の場合は、プライバシーを確保できる構造であることが必要です。
- 自宅の一部やシェアオフィスでも、独立性・専用性・継続性が確保されていれば認められるケースがあります。
- 日単位の短期利用やフリーアドレスのみで区画が固定されない契約形態は、専用性・継続性の要件を満たしにくく、許可が下りない可能性があります。
また、求職者との面談を行うため、下記のようにプライバシーを守れる環境が求められます。
- 個室やパーティションで仕切られた面談室
- 面談内容が外部に漏れない配置や防音対策
これらが整っていないと、労働局の現地調査で指摘を受ける可能性があります。
必要な設備
- 机・椅子・パソコンなどの基本的な事務機器
- 書類を安全に保管するためのキャビネット
- 面談用の机と椅子
いずれも「実際に業務を行える環境」が整っているかどうかが審査されます。
提出する資料
申請時には、事務所の写真や平面図を提出し、要件を満たしているかを証明しなければなりません。
- 入口の写真
- 執務スペースの写真
- 面談室(プライバシーを確保できる環境)の写真
- 面積を明記した平面図
これらは形式的に提出するだけではなく、専用性・独立性・プライバシー確保といった事務所要件を満たしていることを裏付ける資料として審査されます。
また、労働局によってはキャビネットや書類保管設備などの写真を追加で求められる場合もあります。申請先の労働局に事前確認して準備を進めることが重要です。
有料職業紹介事業の免許取得に必要な資格の準備
有料職業紹介事業を運営するためには、各事業所に職業紹介責任者を1名以上配置することが法律で義務づけられています。責任者は事業の法令遵守や運営管理を担う存在であり、申請時に責任者を置いていない場合は免許が下りません。
資格要件
職業紹介責任者になるために特別な国家資格は必要ありません。要件は以下のとおりです。
- 厚生労働省指定の「職業紹介責任者講習」を修了していること
- 成年に達した後、3年以上の職業経験を有していること
講習の概要
- 開催頻度:全国の主要都市で定期的に開催
- 受講時間:1日(約6時間程度)
- 費用:おおよそ15,000円前後
- 内容:職業安定法や労働関係法令、事業運営上の注意点、トラブル事例の解説など
講習を修了すると修了証が交付され、免許申請時に添付が必要となります。
役割と重要性
職業紹介責任者は、求人・求職の適正処理や記録管理、苦情対応など、事業運営が法令に適合するよう監督する役割を担います。事業所全体のコンプライアンス統括責任者とは異なりますが、人材紹介業務における法令遵守の中心的役割を果たす存在です。
- 法令違反がないよう運営を管理
- 求職者・求人企業からの苦情対応
- 行政からの調査・指導への対応
責任者が不在の状態が続くと、免許の更新が認められなかったり、最悪の場合は事業停止処分となる可能性もあります。
有料職業紹介事業の免許取得に必要な書類の準備
有料職業紹介事業の免許を申請する際には、複数の書類を整えて労働局へ提出する必要があります。これらは単なる形式確認ではなく、要件を満たしているかを証明する根拠資料として扱われるため、正確に準備することが重要です。
主な提出書類
- 許可申請書(様式第1号)
職業紹介事業の基本情報を記載する申請書です。
- 登記事項証明書(法人の場合)
会社の存在を証明するもので、法務局で取得します。
- 財産に関する証明書
貸借対照表や残高証明書など、財産要件(純資産500万円以上・現金150万円以上)を証明するための資料。
- 定款の写し
事業目的に「有料職業紹介事業」と明記されている必要があります。記載がない場合は定款変更が必要です。
- 事務所の写真・平面図
入口・執務スペース・面談室を撮影した写真、面積を明記した平面図を提出します。
- 職業紹介責任者講習の修了証
責任者が講習を修了していることを証明します。
提出先と窓口
書類は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の需給調整事業課に提出します。
- 東京都の場合:「東京労働局 需給調整事業課」
- 大阪府の場合:「大阪労働局 需給調整事業課」
管轄ごとに補足資料の指定やフォーマットの違いがあるため、事前に労働局へ相談して確認しておくことが安心です。
有料職業紹介事業の免許申請の流れ
お金・場所・資格・書類の準備がすべて整ったら、いよいよ免許申請に進みます。有料職業紹介事業の申請は管轄の労働局に行い、許可証(免許証)の交付までに通常2〜3か月程度かかります。具体的な流れは以下のとおりです。
申請書類の作成・提出
準備した書類一式(申請書、登記事項証明書、財産証明、定款、事務所写真・平面図、職業紹介責任者講習の修了証など)を管轄労働局の需給調整事業課に提出します。
労働局による審査
労働局では、財産要件・事務所要件・責任者要件を満たしているかをチェックします。
- 書類審査に加えて、現地調査(オフィスの実地確認)が行われることもあります。
- プライバシー確保やオフィスの独立性など、書類だけでは判断できない部分を直接確認されます。
許可証(免許証)の交付
審査を通過すると、有料職業紹介事業許可証(免許証)が交付されます。
有料職業紹介事業は、厚生労働大臣からの許可が交付された日(許可日)から正式に開始可能です。許可証が実際に事業所へ届くのは後日となる場合もありますが、開始の基準日は「許可日」となります。
有料職業紹介事業の免許取得後の更新と注意点
有料職業紹介事業の免許は一度取得すれば永久に有効というわけではなく、新規許可時の有効期間は3年間と定められています。その後の更新からは5年ごとに再度厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
更新の基本ルール
- 有効期間:新規3年/以後5年
- 有料職業紹介事業の更新申請は、有効期限が満了する日の3か月前までに労働局へ提出する必要があります。
- 期限を過ぎると自動的に失効し、事業を継続できなくなるため、早めの準備が重要です。
更新時に必要な書類
更新時には以下の書類を提出します。
- 更新許可申請書
- 直近の決算書(財産要件を満たしているか確認される)
- 事務所の写真・平面図(変更がある場合)
- 職業紹介責任者が引き続き配置されていることを示す資料
登録免許税9万円の納付が必要なのは新規許可申請時のみです。更新時には登録免許税の納付は不要です。なお、新規許可申請時の納付方法は収入印紙ではなく、銀行や税務署での現金納付(領収証添付)が原則となっています。
更新が認められないケース
以下のような場合、更新が不許可となる可能性があります。
- 財産要件を満たさなくなっている(債務超過など)
- 職業紹介責任者が不在のままになっている
- 違法な手数料徴収や不適切な紹介で行政指導を受けている
- 事務所要件が変更されて基準を満たしていない
注意点
- 責任者が退職・異動した場合は、速やかに新しい責任者を講習受講させる必要があります。
- 収益を安定させるために広告費や人件費を確保しておくことも継続のポイントです。
- 行政からの指導に対応せず放置すると、更新拒否や事業停止につながるリスクがあります。
有料職業紹介事業に関するよくある質問(FAQ)
A. 有料職業紹介事業には大きく2つの運営スタイルがあります。
・登録型(データベース型):求職者に登録してもらい、求人企業にマッチングする方式。主に中途採用に活用され、スピード感やコスト効率を重視した採用に適しています。
・サーチ型(ヘッドハンティング型):担当者が市場から候補者を探し出し、企業に紹介する方式。専門職や管理職採用に強みがあります。
どちらも同じ免許で運営でき、法的な要件に違いはありません。
A. 準備開始から免許証交付まで、スムーズに進んでも3〜6か月程度かかります。下記は開業までの動きの一例です。
・1か月目:事務所契約・資金準備
・2か月目:職業紹介責任者講習を受講(※免許申請時に修了証の提出が必要となるため、早めの受講が推奨されます)
・3〜4か月目:必要書類を作成し労働局に申請
・5〜6か月目:労働局による審査・現地調査 → 免許証交付
開業予定日から逆算して、余裕を持って準備を進めることが重要です。
A. 代表的な失敗例は以下のとおりです。
・財産要件を満たしていない(基準資産額が500万円未満である、または現金・預金150万円を下回っている)
・事務所の面積や間取りが基準を満たさず差し戻し
・職業紹介責任者の講習を受け忘れ、申請が遅れる
・定款に「有料職業紹介事業」と記載がなく、定款変更が必要になった
これらを防ぐためには、事前に労働局へ相談して確認しておくことが効果的です。
まとめ:有料職業紹介事業について理解しよう
有料職業紹介事業を始めるには、厚生労働大臣の許可(免許)の取得が必須です。財産要件(純資産500万円以上・現金150万円以上)、事務所要件(おおむね20㎡以上の広さ、またはパーティション等でプライバシーを確保できる環境)、職業紹介責任者の配置、必要書類の整備など、複数の条件を満たす必要があります。
免許申請には登録免許税や講習費、オフィス契約費用などの初期費用がかかり、開業後は求人広告費や人件費などの運転資金も必要です。準備から免許交付までは3〜6か月程度を見込むのが一般的です。
免許の有効期間は新規許可時は3年間、その後は5年ごとに更新が必要です。更新時には財産要件や職業紹介責任者の配置なども再度確認され、基準を満たしていなければ更新が認められないこともあります。したがって、開業後も継続的に体制を整えておくことが重要です。
有料職業紹介事業は、求人企業と求職者を結びつける社会的意義の高いビジネスです。しっかりと準備を整えれば、比較的少ない初期投資でスタートでき、専門性を活かした人材紹介サービスを展開することが可能です。開業を検討している方は、本記事を参考に準備を進め、スムーズに免許取得を実現してください。
クラウドエージェントは、人材紹介会社向けに10,000件以上の求人を提供する求人データベースです。
全国の幅広い業界・職種の求人を取り扱っており、自社だけでは開拓が難しい案件にもすぐアクセス可能。
求職者への提案力を高めたい方、効率的にマッチングを進めたい方は、ぜひクラウドエージェントをご活用ください。
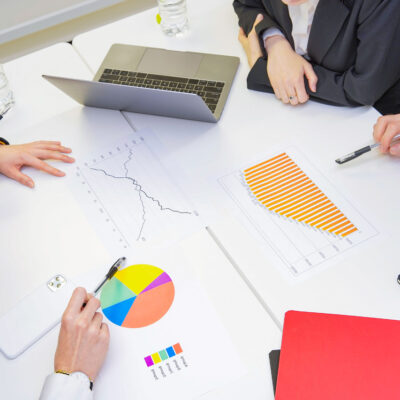






























この記事へのコメントはありません。